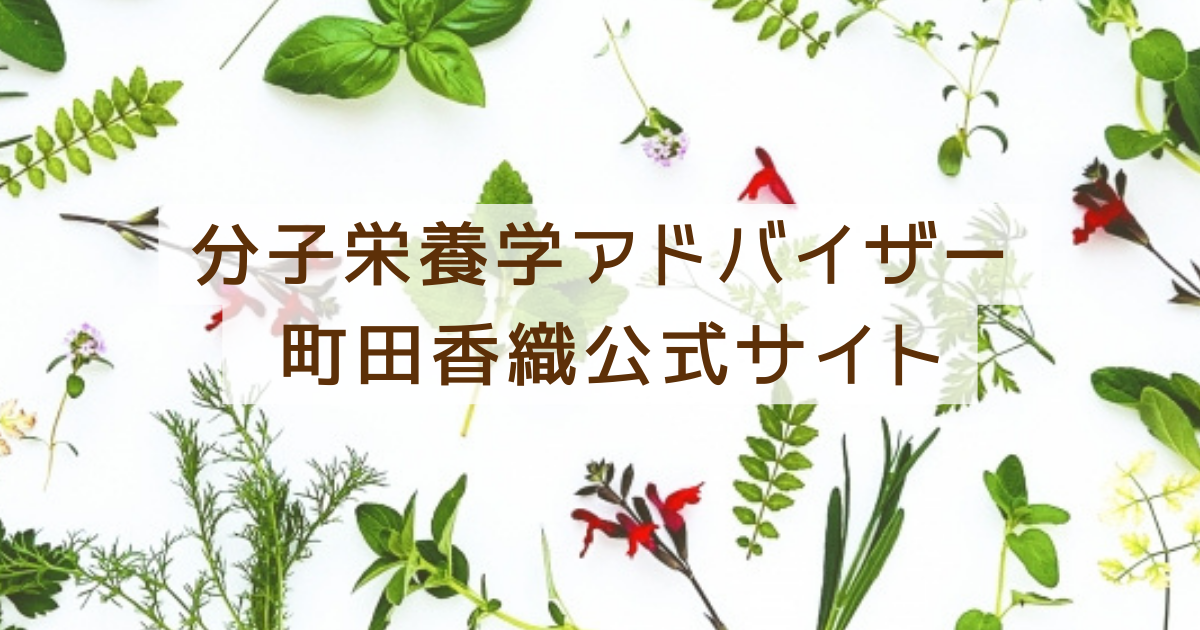「分子栄養学」とは
分子栄養学とは、ノーベル化学賞を受賞したライナス・ポーリング博士が提唱した、革命的な医学の考え方で正式には、分子整合栄養医学(オーソモレキュラー)と言います。
※オーソ(ortho)とはギリシャ語で「正しい」
モレキュラー(molecular)は「分子」という意味をつなぎ合わせた造語です。
ひとりひとりの「個体差」をみながら、細胞(分子)レベルで体を元気にしていく栄養学で、元々、自分が持っている自然治癒力を高め、病気を改善していくだけではなく、未病を防ぎ、健康増進に導いていく考え方です。

従来の栄養学の考え方では、栄養素が補えていない方々がいる
従来の一般的な栄養学では、健康的な生活を送るため、もしくは病気にならないための「必要最低限の栄養素」の量を指標としています。

出典:農林水産省Webサイト(https://www.maff.go.jp/j/balance_guide/)
しかし、その指標だと「本当に必要な栄養素が圧倒的に足りない」という方が多数おられます。その人にとって必要な栄養素の量というのは、一人ひとり個体差があるのです。
その人の食生活はもちろん、年齢、体の大きさ、生活スタイル、ストレス度、更にはその人が抱える悩みや病態などによって摂取が必要な栄養素が変わってきます。加えて、ある栄養素が欠乏している人にとっては、推奨摂取量よりも多めに摂取する必要があります。
分子栄養学を用いた栄養カウンセリングでは、ひとりひとりのその「個体差」(年齢、性別、遺伝的要因、ストレス、成長期、妊娠、病気、生活習慣、活動量、食事内容、腸内環境、消化力、など)を細かくヒヤリングし、食事や生活習慣の改善をご提案していきます。

通常の医療は、臓器別医療で、その視点だと「木を見て森を見ず」になっている可能性があります。
人間の体を、約37兆個の細胞ととらえ、一つ一つを元気にしていく分子栄養学の考え方は「木を見て、森も見る」という視点での栄養学と言えます。